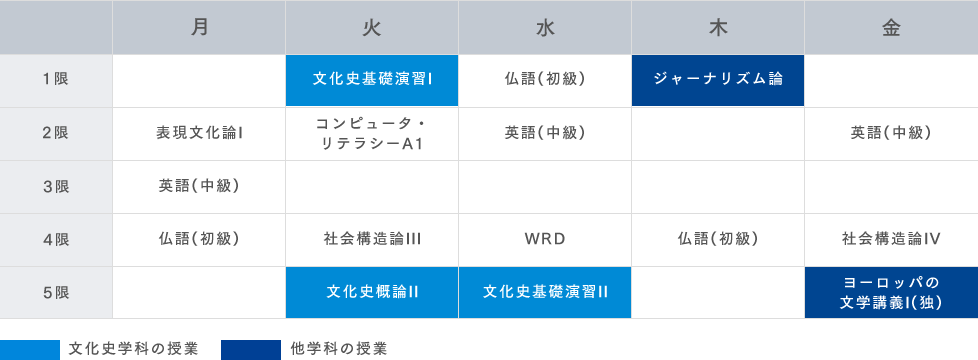文化史学科
学科紹介
私たちの学科では、日々の衣食住や生活習慣、信仰などの身近なことから、ひろく社会や政治・経済、環境問題にいたるまでの人間の営みの総体を「文化」と捉えます。そうした広い意味での文化を、歴史的な変遷をよみとって研究します。
たとえば、みなさんが日常的に利用しているSNSは、現代の情報化と技術革新のなかで出現・進化し、私たちの日常生活における新たな習慣やライフスタイルを生み出しています。その一方で、SNSを通したコミュニケーションは、人と人とのつながりをめぐる歴史的変遷の一コマとして捉えることもできます。このような文化史の学びを深めるため、私たちの学科では、日本史学・民俗学・文化人類学という3つの学問分野をともに学ぶことができる独特のカリキュラム編成を行っています。
文化史学科は、私たちが直面する(直面した)さまざまな問題を多角的・多面的に分析し、混迷する現代社会を一人ひとりがよりよく生きていくための学びをめざしています。


「文化」を学ぶ
政治・経済・社会などの分野を超えて、「文化」という総合的な視点から日本の歴史を学びます。

「見る・聞く・感じる」
過去から現在に至る人々の日常生活の移り変わりを、「見る・聞く・感じる」ことを通して学びます。

相互理解を深める
世界中に広がる文化と社会の比較を通して、共通すること/異なることに気づき、相互理解を深めます。
船は漁師にとって命を預ける大切な存在。船の名前、とくに娘や妻など、家族の女性の名前をつけることが多かったのはなぜでしょう。
最近はペットも家族と言われますが、人間の家族とペットとの扱いの決定的な違いはどんなところに表れるでしょうか。
食べ物の地域的特色は、現代のファストフード化で喪失するかというと、そうとは限りません。ご当地グルメのように、メディアを通じて新たな地域差が生み出されていくこともあります。
1年次で身につけた歴史学・民俗学・文化人類学に関する基礎的な知識をより確かなものにするための実習でフィールドワークを実施し、資料収集の基礎作業や調査報告書の記述方法まで一貫した流れを学びます。
毎年、それまでに学んできたことを実地に体験し、学生相互あるいは学生と教員の親睦を深めるために、3年次学生全員が参加する「文化史学科研修旅行」(2泊3日)を実施しています。
日本民俗学の創始者・柳田國男の寄贈書を収めた「柳田文庫」を基板とした知の宝庫「民俗学研究所」と、世界的にもユニークな「グローカル研究」を構想し、推進する「グローカル研究センター」があります。
文化とは、人間が積み上げてきた知識と知恵の総体です。
その文化の多様性を学び、現代社会の成り立ちを理解するのが本学科の目的です
複数の視点から、日本、さらには東アジアの生活・文化の発生・変遷、そして現代社会とのつながりを考えます。
体験的・実践的な研究を重視し、さまざまな機会を捉えて、現地調査を行います。
学科単位の研修旅行も実施します。
| 概論科目 |
|
|---|---|
| 実習科目 |
|
| 演習科目 |
|
| 講義科目 |
|
| 自由科目 |
|
| ゼミナール |
|