

NEWS
2025.08.27
成城大学スポーツとジェンダー平等国際研究センターが受託している令和7年度スポーツ庁事業「令和7年度 スポーツ国際展開基盤形成事業におけるスポーツ国際政策推進基盤の形成:政府間会合の合意事項の履行Bタイプ」の一環として2025年7月8日〜11日にかけて、野口副センター長、宮澤ポスドク研究員、古田ポスドク研究員がソウル国立大学(大韓民国)で開催された国際スポーツ社会学会(The International Sociology of Sport Association, ISSA)主催の「2025 World Congress of Sociology of Sport “60 Years of the Sociology of Sport: Past, Present, and Future Trajectories”」に参加し、スポーツ庁委託事業『令和6年度ポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業「スポーツにおけるジェンダー平等推進事業」』における現地調査の研究報告をしました。
■ 学会概要
本大会は「60 Years of the Sociology of Sport: Past, Present, and Future Trajectories(スポーツ社会学の60年:過去・現在・未来の軌跡)」をテーマに掲げ、世界各国からスポーツと社会の関係に関心を持つ研究者が集まりました。開催地となったソウル国立大学には、イギリス、カナダ、アメリカをはじめ、日本、台湾、オーストラリアなど、アジア開催ならではの参加も目立ち、数百名の研究者が参加しました。会場では、多様な地域・文化的視点からの研究発表が行われ、活発な議論が展開されました。

ソウル国立大学校舎に掲げられた学会大会の横断幕
本大会のパネルディスカッションでは、グローバル・サウスにおけるスポーツと社会課題、気候変動との関係、ジェンダーの視点、そしてアジアからの学術的発信など、幅広い社会的テーマが取り上げられました。全体では36のセッションテーマが設けられ、254件の口頭発表と43件のポスター発表が行われ、なかでもスポーツとジェンダーに関する発表が最多を占めました。また、多くのセッションで実践と研究の接続が重視され、理論と現場を架橋する取り組みが数多く見られました。
本発表では、古田ポスドク研究員がプレゼンターを務め、「An Ecological Perspective on Women's Participation in Sports: Case Studies from Brunei, Cambodia, and Malaysia」というタイトルのもと、令和6年度ポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業「スポーツにおけるジェンダー平等推進事業」の一環として2024年度に実施された調査の成果を報告しました。発表では、ブルネイ、カンボジア、マレーシアを対象とした調査に基づき、女性のスポーツ参加を阻むさまざまな障壁についての報告を行いました。
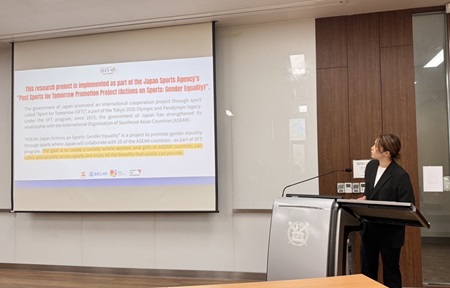
発表の様子:古田ポスドク研究員
古田ポスドク研究員は、現代スポーツが西洋の影響下で世界に広がった歴史を踏まえ、女性のスポーツ参加に関する研究の多くが欧米を中心に進められてきた一方で、アジア地域、とりわけその社会的・文化的文脈に根差した研究が依然として少ないことを指摘しました。また、地域に固有のジェンダー規範が女性の可能性や選択肢を形成しており、スポーツへのアクセスは社会的・経済的・宗教的・文化的要因に大きく影響されると述べました。
そのうえで、女性のスポーツ参加を促進するには、地域の現実に即した理解と、具体的な障壁の把握が不可欠であると強調しました。真に包摂的なスポーツ環境を実現するには、文化的・構造的な変革が必要であり、地域に根ざしたアプローチが重要だと訴えました。今後は、ASEAN各国の状況をより深く理解し、各地域の文脈に応じた政策形成を支援するとともに、共通課題の抽出を通じて国際的な議論にも貢献していきたいと展望を語りました。
発表後の質疑応答では、本研究の学術的・社会的意義や、今後の展開について活発な議論が交わされました。特に、ヨーロッパ諸国を中心とした従来のジェンダー研究との比較において、東南アジア特有の文化的・社会的文脈をどのように位置づけるかという点に関心が集まりました。
また、本研究が単なる記述的な調査にとどまらず、政策提言やジェンダー主流化(gender mainstreaming)を推進するという本事業の目的を明確に意識したものであることが再確認されました。議論では、アジアの多くの国々に見られる集団主義的な価値観や歴史的・文化的背景を踏まえたアプローチの必要性も共有され、国民国家的な枠組みや規範の違いを尊重しながら、各国に適した形でのスポーツ政策やジェンダー平等の実現を目指すことの重要性が改めて強調されました。
今回の学会参加を通じて、平和と開発のためのスポーツ分野やスポーツとジェンダー分野で国際的に活躍されている研究者とつながることができ、今後のアジア地域における学術的知見の蓄積や協働の可能性についても議論を交わしました。今後は、SGEがアジアにおけるハブとしての役割を果たし、国際的な議論の発展に貢献していくことを目指します。