

NEWS
2018.03.26
3月22日(祝)、「里神楽ワークショップ in 成城大学 — 生きている神楽 -」を開催しました。
神楽は、天岩戸神話で天照大神の関心を引くための天宇津女命の舞が発祥とされる日本最古の芸能と言われ、宮中の御神楽(みかぐら)に対し、民間の祭祀などで演じられるものを里神楽といいます。「より近くで神楽を楽しんでファンになってもらいたい」と江戸里神楽公演学生実行委員会を務める成城大学の学生が中心となりこのイベントを企画し、相模里神楽 垣澤社中の垣澤瑞貴さんをお招きしました。当日は季節外れの雪という悪天候でしたが、定員を上回る50名以上もの参加がありました。
まずは、主に中国地方の里神楽を研究している俵木悟准教授(文芸学部文化史学科)から神楽の歴史と変遷に関するミニ講義がありました。語源や種類(獅子舞も神楽の一種だそうです)、神楽の持つ意味についてなど、大変興味深いお話しでした。
続いて、相模里神楽 垣澤社中の垣澤瑞貴さんによる実演とワークショップ。笛や舞の種類について実演を交えながら分かりやすく解説していただき、さらには古事記を元に垣澤さんが創作した新神楽舞「木花咲耶姫」をご披露いただきました。また、参加者全員で簡単な所作も体験しました。
最後は、江戸流の里神楽を中心に研究している田村明子研究員(成城大学民俗学研究所)が進行役となり、垣澤さんと俵木准教授による対談が行われました。女性神楽師の誕生や創作神楽など時代による変遷の話題から、神楽は守るべき古き良き伝統というだけではなく、現在も「生きている」ものであるというお話しとなりました。
企画、準備、当日の司会やパンフレット作成など、すべて成城大学の学生が行いました。「楽しくて分かりやすい」をスローガンに活動している江戸里神楽公演学生実行委員会委員長の馬場綾音さん(文芸学部国文学科3年)は、「準備は大変でしたが、多くの方に熱心に参加していただけて本当に嬉しかった」「堅苦しいと感じている若い世代にも民俗芸能の熱を広げたい」と話していました。

俵木准教授によるミニ講義「神楽の歴史と変遷」

垣澤瑞貴さんのお話し



数種の笛や舞の種類について実演を交えてご紹介してくださいました


新神楽舞「木花咲耶姫」。強く気高き桜の女神の物語。


「木花咲耶姫」のラストには役者として垣澤さんの愛娘も登場。
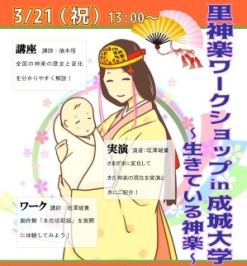
これがポスターの絵です。

対談も大変面白いお話しでした。

法被姿で手伝った学生たち

全体の司会・進行も学生が行いました

準備や片付けも手伝います

ケーブルテレビの取材も受けました
里神楽ワークショップ in 成城大学 — 生きている神楽 -
日時:2018年3月21日(水・祝) 13:00~15:30
内容:神楽講座&ワークショップ
第1部 講義「神楽の歴史と変遷」
講師・俵木悟(成城大学文芸学部文化史学科 准教授)
第2部 実演&ワーク「神楽の現在と未来」
演者・垣澤瑞貴さん(相模里神楽 垣澤社中)
第3部 出演者対談
俵木悟・垣澤瑞貴さん 進行:田村明子(成城大学民俗学研究所研究員)
主催:江戸里神楽公演学生実行委員会
協力:成城大学民俗学研究所